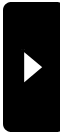【天体観測】しぶんぎ座流星群2019【解説編】
流星群キャンプから帰ってきたばかりのこーりんです。
今回はしぶんぎ座流星群について解説します。
できればこういう企画って前もって書く方が良さそうですが、
大体思い付きで書いているので・・・直さないとねw
今回は1/4に極大を迎えました「しぶんぎ座流星群」の解説をしますが、
まず「流星群って何?」という所から軽く説明していきます。
※今回は説明文ばかり&キャンプの内容ではありませんが、
天体観測もキャンプの楽しみのひとつと考えています。
内容が合わない方には申し訳ありません。

(出典:君の名は。) こちらは隕石ですが・・・
お品書き
1.流星群って何?
2.じゃあ星座の名前は何?
3.「放射点」って?
4.なんでチリが多い場所があるの?
5.今回の流星群は?
6.結果はどうだったの?
1.流星群って何?
夜空を眺めているとたま~に流れ星が見えることがあります。
あの流れ星は、宇宙に漂うチリや石が地球の引力に吸い寄せられ、
大気と衝突する時に発する光が見えています。
(細かく言うとプラズマ化とか圧縮熱とかありますが・・・)
・・・つまり、チリが地球に落ちてくれば流れ星になります。
チリが多い場所を地球が通過するとき、たくさんのチリが地球に落ちてくるので
流れ星が多く見える=流星群、となります。
2.じゃあ星座の名前は何?
今回だけでなく、殆どの流星群は星座の名前が付いています。
夜空にはすべての空域に88星座の領域が割振られています。
流星群の名前は流星群の流れてくる中心「放射点」の
ある星座の名前が付いています。
ただ、今回の「しぶんぎ座」は88星座には含まれません。
昔しぶんぎ座と呼ばれていた場所に放射点があるので
そのまま呼ばれています。
3.「放射点」って?
放射点とは流星群の流れてくる大体の中心点の事です。
流星群が出現している時、流れ星1つ1つは様々な方向に流れますが、
流れてくる場所を 辿っていくとある一点から流れているように見えます。
この中心を放射点と言います。
大体の中心なので、必ずここから流れるわけではありません。
4.なんでチリが多い場所があるの?
流星群の材料となるチリは、主に「彗星」が落としたものと考えられています。
彗星が通った場所にチリが残り、そこを地球が通過した時に流星群となって現れます。
そんな理由もあって毎年同じ時期に同じ星座から流れてくるように見えます。
昔はこのチリを落とした彗星の名前(ジャコビニ流星群とか)が付いていましたが、
近年では全て星座の名前が付いています。
5.今回の流星群は?
今回の流星群を表で表すと・・・
活動期間は半月ほどあります。
極大時以外は数は少ないですが、普段より見つけやすいでしょう。
月あかりがほぼないので観測には適しているでしょう。
ZHRは120と多いので見つけやすいでしょう。
極大時は日本では昼間になります。極大前の1/4夜明け前が最も多く見えたでしょう。
・・・と、天気予報風に解説してますが、分からないですねw
まず活動期間ですが、流星群はその日だけの現象ではなく
だんだん増えていって極大(ピーク)を過ぎたらだんだん少なくなるので、
モノによっては1ヶ月以上の期間があったりします。
なので極大を過ぎたから見れないという事はなく、
今回の私のように1日遅れでも十分見ることができます。
夜空の観測は暗い方が良いので月明かりがない方が見やすいですね。
月相(月齢)とは月の大きさを0~29くらいまでの数字で表します。
0は新月、14~15くらいが満月で29くらいで新月に戻ります。
つまり月は0に近い程暗く、15に近いほど明るい事になります。
最後は天頂出現数(ZHR)です。
流星群は放射点が天頂(一番高いところ)にあると一番多くなると言われています。
この状態で1時間あたりに見える理論的な最大数をZHRと言い、
数字が大きい程たくさんの流星が見える(と思われる)ため、
流星群の規模が表せる数字になっています。
ZHR120は年間通して最も多い数字で、安定して流星が見れると考えられます。
6.結果はどうだったの?
今回、結果から言えば「個人としては成功」と言えるでしょうか。
私は1/3に私用があったため1/4の明け方は見ることができず、
極大を過ぎた1/4、21時過ぎから2時間ほど観測してました。
山あいのキャンプ地だったので、放射点が山で隠れてしまいました。
放射点が見えるころには明け方になってしまう場所だったので、
あまり見ることができないかもと思ってましたが、
小さな流星でしたが十数個見ることができ、中には長い流星もありました。
ただひとつ、カメラを持って行かなかったので写真がないことが悔やまれます。
(おかげで文字ばかりのレポートです・・・)
おわりに
長々と解説ばかりしましたが、ぼーっと夜空を眺めるのも楽しいですよ?
遠くに出かけなくても自宅や公園でも見上げるだけで自然に触れ合えるし、
時間や季節によって移り変わるので飽きずに楽しめます。
それにただ見てるより星が読めると子供やパートナーにちょっと自慢できるかも。
今後もキャンプしながら何かあればレポート&ご紹介していきます。
文字だらけの解説回、今日はこのあたりでおしまいです。
ではまた次回!
今回はしぶんぎ座流星群について解説します。
できればこういう企画って前もって書く方が良さそうですが、
大体思い付きで書いているので・・・直さないとねw
今回は1/4に極大を迎えました「しぶんぎ座流星群」の解説をしますが、
まず「流星群って何?」という所から軽く説明していきます。
※今回は説明文ばかり&キャンプの内容ではありませんが、
天体観測もキャンプの楽しみのひとつと考えています。
内容が合わない方には申し訳ありません。

(出典:君の名は。) こちらは隕石ですが・・・
お品書き
1.流星群って何?
2.じゃあ星座の名前は何?
3.「放射点」って?
4.なんでチリが多い場所があるの?
5.今回の流星群は?
6.結果はどうだったの?
1.流星群って何?
夜空を眺めているとたま~に流れ星が見えることがあります。
あの流れ星は、宇宙に漂うチリや石が地球の引力に吸い寄せられ、
大気と衝突する時に発する光が見えています。
(細かく言うとプラズマ化とか圧縮熱とかありますが・・・)
・・・つまり、チリが地球に落ちてくれば流れ星になります。
チリが多い場所を地球が通過するとき、たくさんのチリが地球に落ちてくるので
流れ星が多く見える=流星群、となります。
2.じゃあ星座の名前は何?
今回だけでなく、殆どの流星群は星座の名前が付いています。
夜空にはすべての空域に88星座の領域が割振られています。
流星群の名前は流星群の流れてくる中心「放射点」の
ある星座の名前が付いています。
ただ、今回の「しぶんぎ座」は88星座には含まれません。
昔しぶんぎ座と呼ばれていた場所に放射点があるので
そのまま呼ばれています。
3.「放射点」って?
放射点とは流星群の流れてくる大体の中心点の事です。
流星群が出現している時、流れ星1つ1つは様々な方向に流れますが、
流れてくる場所を 辿っていくとある一点から流れているように見えます。
この中心を放射点と言います。
大体の中心なので、必ずここから流れるわけではありません。
4.なんでチリが多い場所があるの?
流星群の材料となるチリは、主に「彗星」が落としたものと考えられています。
彗星が通った場所にチリが残り、そこを地球が通過した時に流星群となって現れます。
そんな理由もあって毎年同じ時期に同じ星座から流れてくるように見えます。
昔はこのチリを落とした彗星の名前(ジャコビニ流星群とか)が付いていましたが、
近年では全て星座の名前が付いています。
5.今回の流星群は?
今回の流星群を表で表すと・・・
| 名称 | しぶんぎ座流星群2019 |
|---|---|
| 活動期間 | 12/28~1/12 |
| 極大 | 1/4 11:00頃 |
| 天頂出現数 (ZHR) | 120 |
| 月相(月齢) | 28 |
| 日本での見頃 | 1/4 夜明け前 |
活動期間は半月ほどあります。
極大時以外は数は少ないですが、普段より見つけやすいでしょう。
月あかりがほぼないので観測には適しているでしょう。
ZHRは120と多いので見つけやすいでしょう。
極大時は日本では昼間になります。極大前の1/4夜明け前が最も多く見えたでしょう。
・・・と、天気予報風に解説してますが、分からないですねw
まず活動期間ですが、流星群はその日だけの現象ではなく
だんだん増えていって極大(ピーク)を過ぎたらだんだん少なくなるので、
モノによっては1ヶ月以上の期間があったりします。
なので極大を過ぎたから見れないという事はなく、
今回の私のように1日遅れでも十分見ることができます。
夜空の観測は暗い方が良いので月明かりがない方が見やすいですね。
月相(月齢)とは月の大きさを0~29くらいまでの数字で表します。
0は新月、14~15くらいが満月で29くらいで新月に戻ります。
つまり月は0に近い程暗く、15に近いほど明るい事になります。
最後は天頂出現数(ZHR)です。
流星群は放射点が天頂(一番高いところ)にあると一番多くなると言われています。
この状態で1時間あたりに見える理論的な最大数をZHRと言い、
数字が大きい程たくさんの流星が見える(と思われる)ため、
流星群の規模が表せる数字になっています。
ZHR120は年間通して最も多い数字で、安定して流星が見れると考えられます。
6.結果はどうだったの?
今回、結果から言えば「個人としては成功」と言えるでしょうか。
私は1/3に私用があったため1/4の明け方は見ることができず、
極大を過ぎた1/4、21時過ぎから2時間ほど観測してました。
山あいのキャンプ地だったので、放射点が山で隠れてしまいました。
放射点が見えるころには明け方になってしまう場所だったので、
あまり見ることができないかもと思ってましたが、
小さな流星でしたが十数個見ることができ、中には長い流星もありました。
ただひとつ、カメラを持って行かなかったので写真がないことが悔やまれます。
(おかげで文字ばかりのレポートです・・・)
おわりに
長々と解説ばかりしましたが、ぼーっと夜空を眺めるのも楽しいですよ?
遠くに出かけなくても自宅や公園でも見上げるだけで自然に触れ合えるし、
時間や季節によって移り変わるので飽きずに楽しめます。
それにただ見てるより星が読めると子供やパートナーにちょっと自慢できるかも。
今後もキャンプしながら何かあればレポート&ご紹介していきます。
文字だらけの解説回、今日はこのあたりでおしまいです。
ではまた次回!